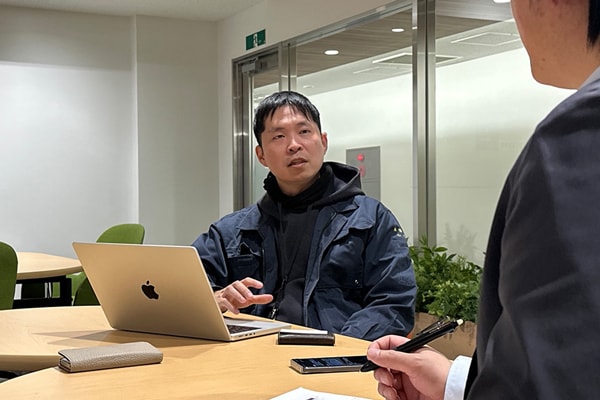【クリエーターたち】合同会社 Fielder's 代表 / 技術士 淵岡弘幸 インタビュー
「つくりたい」という想いを胸に挑戦を続ける、色とりどりのつくり手たち。
困難や失敗を乗り越えて、想い描いたビジョンをカタチに変えていく。工夫や探求を積み重ね、新たな価値を生み出していく。そんな、つくり手という生き方。その軌跡と想いをひも解くインタビュー。
今回は、京都出身でありながら広大な南アルプスを望む自然の中でものづくりに没頭する Fielder's の淵岡弘幸さんにお話を聞きました。

淵岡・弘幸(ふちおか・ひろゆき)
1964年、京都府生まれ。関西大学機械工学部・大学院修了。国家資格である公益社団法人日本技術士会 技術士(機械部門)の資格を保有。大手機械メーカー開発部門に長年勤務した後、2012年に京都市で技術士事務所 株式会社BUCを設立し、大阪工業大学の非常勤講師を2015年~2018年に兼務。2017年に長野県伊那市の土地を購入し、2拠点生活を開始。2020年、伊那市で Fielder's(フィールダーズ)を設立。
合同会社 Fielder's
2020年4月に長野県伊那市で設立。「SLOW FIELD LIFE ~風を楽しみ、自然と共に生きよう~」というテーマのもと、庭、ウッドデッキ、畑、狩猟など、それぞれのフィールドを満喫するのに役立つツールを開発し提供している。こだわりは「今までありそうでなかった、かゆいところに手が届く、独創的な製品」を提供すること。アイデア発想と設計を淵岡さん、組立、検査、梱包に至るまでを淵岡さん御夫婦で手がける。
▶ 公式サイトへ
京都から長野へ。自然のなかで見つけた、新たな挑戦とものづくりのテーマ。
独立して京都でひとつめの会社をしてたときに、設計の同業者からお声がけいただいてとある大学の地域活性化ワークショップに参加しました。そこで獣害についての切実な悩みを伺って、後日に若手猟師の方とお話しした際に「ハンターxハンガー」という製品の企画が立ち上がり、この製品の開発が長野で Fielder's を立ち上げるきっかけになりました。
製品を作る工程で、試作ができたら評価しますよね。「ハンターxハンガー」を評価するのに土と木が必要やったんですが、京都にはそれがなかったんです。鴨川の河川敷とかも考えたんやけど、河川敷は国のものやから勝手に使うわけにはいかへんなと。だから最初は知り合いに土地を貸りて評価してたけど、やっぱり自分とこで評価したいやないですか。そこで伊那で試してみたところ、ちゃんと評価できたんですわ。それで、ここを拠点にものづくりをしようと思たんです。
長野はもともと好きやったからね。いつか長野で暮らせたらっていう漠然とした夢は結構前からあったんです。けど実際ここに来ることになったきっかけは京都で仕事が立て込んだときに、どうにも忙しくて疲れて逃げ出したくなって。ちょっといいところを探すかってことで妻と2人で土地を探しだしました。絶対条件は「山が綺麗に見えること」あとは「京都に通える距離」「雪が多すぎない場所」で絞り込んで、南アルプスが綺麗に見えるこの土地を見つけたんです。

淵岡さんがこの土地に移住するきっかけとなった南アルプスの山並みの綺麗な風景
一番大きな変化は自然との距離が近くなって、自然をより積極的に楽しむためのものを作るようになったことやね。この環境にいると、人間ちゅうのはほんまは自然の中で生きる動物なんやなぁ、というのを強く感じます。自然との距離が近くなったことで、僕のものづくりに「つくるテーマ」が生まれました。
こっち来て最初はただ単に欲しいものをつくってたんやけど、あるときふと、これが社会的にいったい何の役に立つんやろうと思って。そこから考えていくうちに、自分のものづくりを通じて世の中に何か新しいライフスタイルを提案できたら、と思うようになりました。それで「田舎暮らしを楽しく」というキーワードと、「SLOW FIELD LIFE」という Fielder's のテーマができました。
テーマができると方向性も明確になって、自分が何のためにものづくりをしてるのか説明しやすくなりました。長野に来る前は「頼まれたから作る」いう感じやったんですけど、Fielder's では「この環境をもっと楽しんだり味わえるもの」を作るようになりました。せっかくこんな環境に居るんで、色んなことを無駄にしたくないなぁと思てます。
「自由に作る楽しさ」から始まった、淵岡さんのものづくり人生。
子どもの頃はプラモデル作ったり夏休みの工作やったり、自由に作れるのが好きやったね。授業の図工とか工作なんかは、時間もやり方も決まってるんであんまり好きやなかった。プラモデルのほか、ラジコンも作ったしNゲージやジオラマとかの模型も好きで、そういう中で生きてました。
大学では機械工学、大学院では計測工学を専攻しました。計測工学は光学寄りの分野で、PC を使って演算を取り入れるような研究ができるのが魅力でした。当時は PC が出始めた頃で、まだ個人で所有できるような時代やなかったんです。プログラムも MS-DOS 上で動かしていて、Windows なんか影も形もなかった時代です。今でも光学機械の設計は得意なジャンルで、大手光学機器メーカーなどから仕事を頂くことがあります。
大手重工メーカーに入社して、商業用のどでかい製紙機械を開発する部署に配属されました。社会人としての基礎はここでみっちり叩き込まれましたね。入社してすぐは、どうやったら良い紙が作れるかという、紙の要素研究から始まりました。そこから徐々に設計にも携わり、最終的には次世代の製紙機械の設計開発を担当しました。けどとてもでかい機械やったんで、自分で設計したのに自分で組まれへん。それはやっぱりおもろないし、自分が作りたい機械とちがうなと。

全部自分でできるっちゅうのが、僕にとってはオモシロい。
それで次の会社は BtoB 向けの中〜少量生産の機械を開発しているとこに移って、業務用のスキャナー、レーザー露光機、インクジェットプリンター等の設計をしました。加えて前の会社は業務上の役割や関われる領域がほぼ決まっていたのに比べて、次の会社ではやりたかったら何でもできるのが性に合ってました。僕、首突っ込みな性分で(笑)困っている部署があれば顔を出して、一緒に考えたりするのが好きやったから。
最初はいちメンバーやったけど最後はプロジェクトリーダーもやったんで、その時はもう企画から最後の責任とるとこまで全部やっていって。ものを作る一連の流れをそのときに勉強したことが、今のものづくりにもつながってるんかなと思います。
やっぱり自分でつくったものを自分で売るとなると、次元が一段階変わるんです。会社でもずっとものづくりをやってきて色々なことに携わったけど、それでもまだ僕が深く携わらない領域があるんです。梱包とか取扱説明書とか。
いまやってるものづくりは、保守やメンテナンス、寿命、使い勝手、安全性、 梱包や取扱説明書。全っ部自分でちゃんとやらなあかんのですよ。あたりまえやけど(笑)面倒くさいし大変なんやけど、そこまで全部できるというのが、僕にとっては面白いしやりがいがある。
オリジナルマインドさんのマインドは僕も分かる気がします。モノからすごい伝わってきます。たぶんね、考え方が似てると思うんですよ。要するに「かゆいところに手が届く」というか、「ありそうでなかったもの」を作っておられる。言うたら、個人と大企業のはざまのモノですよ。「やられた!こんなん作ったんか!」って思うときありますもん。
なので僕らみたいな小規模メーカーにとって、オリジナルマインドさんの製品はすごい武器になると思う。組み立てマニュアルも綺麗にできてます。すごいですわ、あれ。僕は印刷したものとタブレット両方を使いながら見てます。大きくして見たいときはタブレット使ってね。それで梱包もよう考えてあります。あれだけ細かい部品もきちんと梱包してあってね。もうこんだけマニュアルとか梱包にお金かけるんやったら、組み立ててから出荷されてもええんちゃうかって思うときもありますけど(笑)
補足:当社では高性能と低価格の両立を図るため、製品を組み立てキット式でご提供しています。詳細は 組み立てキット式による提供 をご覧ください。
ものづくりの方向性と少量生産のポイント
うちで開発しているのは基本的に僕が庭で楽しむために作った、身近なフィールドを起点としたアウトドア用具なんです。そやから一般的なキャンプや登山なんかの「持ち運び」を前提にしたコンパクトさとか軽さとかは二の次です。それより庭でゆったり調理をしたり、愛犬とちょっと散歩をしたり、ウッドデッキで本格バウムクーヘン焼いたりとか、そういう感じなんです。
ちなみに外で食べるものって美味しさが格別なので、野外で炎と食を楽しむアイテムは多いですね。美味しくなる加熱温度とか、旨味を引き出す伝統的なレシピの情報をもとに設計したりします。それを仕上げに良い炭で調理してね。
自分が欲しいものを作るときの熱量は、むちゃくちゃ大きいです。どの商品もめっちゃ売れてます!とは全然言えませんが、どれも僕にとって自慢できる一品です。
各々のお気に入りのフィールドでゆったりした時間を楽しむ「SLOW FIELD LIFE」がテーマなので、そうかもしれません。あとは製品に「つくり手の遊び心」が入れられるのが、うちら小規模メーカーの強みやと思うんですね。大企業じゃできないものを作る。それをしようとするとやっぱり少量生産になるんで、時間とお金が少々かかってもいいから、自分とこでつくれる環境を整えておきたいところです。
まず設計かな。大量ロット前提の部品は使わず、既製品を活かせる部分は活かす。外注部品も、どこに頼んでも安定して少量生産できる形状にします。やないと製造コストがむちゃくちゃ上がってしまうんです。部品点数は極力減らして、シンプルで組み立てやすい設計にします。シンプルなものほど難しい、シンプルにするのが難しいんやけどね。
あと値付けは、基本的に自分がなんぼで買いたいと思うかで決めます。ひとに聞くと判断がブレるし、だいたい「安いほうがいい」って言われるんで(笑)自分がつけたい値段をつけて、それで売れなかったらしゃーないんです。
「空圧式 INARI P35」で開けた、新しい製品開発の可能性。
「ゆきちゃん」は草刈りで苦労しているうちの母ちゃんをみて、これは発明家である自分がなんとかせなあかん!と思ったのがきっかけで開発しました。草刈りで長時間しゃがんでると腰や膝に負担がかかるし、一般的な刈り払い機は重たくてしんどいし危険やし。それらを解消したうえで、手軽で可愛くて玄関先に置いといて気軽に使える草刈り機を目指しました。


新製品の「刈るルン ゆきちゃん」。高さを段階的に調整するためのリング部分や、ハンドルの角度を調整するノブ、車輪を「空圧式 INARI P35」で製作。

底面の刈り刃も「空圧式 INARI P35」で製作。
樹脂部品を外注すると、小さい部品作るんでも成形型代が100万円以上かかって最小発注数が1万個とかやったりします。そんな大量に作っても一気に売れないし、それ使い終わるまでなんもできませんってことになると、次へ進まれへんやないですか。そうじゃなくて、少量作って気づいたことがあったら改善して、在庫も必要な分だけ作って置いとくとか。中小メーカーこそそういった小回り効かせていかなというわけで、これまで樹脂部品はあえて避けてきました。
新しいもの好きなんでかなり前から使ってます。思いついたものをすぐ形にしたり、複雑な形状もパッと作れるのが良い点です。ただそもそも草刈り刃のような強度が必要なものは作ることができないんで、3Dプリンターだけで「ゆきちゃん」を作るのは難しかったですね。
けど「INARI P35」やったら強度も担保できるし、型さえ作ってしまえば数も必要な分だけ作れる。カタチを変える場合も自社でアルミ型作るだけやからすぐやし、外注しなくて良いので高額な型代が不要になったのもとても大きなメリットです。
そこで 3Dプリンターと「INARI P35」の合わせ技でできたのが「ゆきちゃん」です。複雑な凸凹があるカバーや台座の部分は 3Dプリンター、強度を必要とするホイールや刃、高さ調整をするリング部品やノブは射出成形というふうに使い分けて製作しました。
「女性が気軽に使えて、安全でしっかり刈れる」ことを考えて、素材は金属やなく樹脂。機構は衝突時に刃が逃げて衝撃を緩和できるフリー刃機構を採用しました。これによって、草刈り中によくある "キックバック" いう刃が跳ね返ってくる現象が発生せず、安心して使えます。
安全に刈るという点ではナイロンカッター機構もありますが、こちらは切れが悪いです。しかも小石や砂などが飛び散るので、その点において安全性も減点になりますね。
一方、刃先をカッターのように尖らせた樹脂刃なら切れも良く、やや太めの枯れ草などもしっかり刈れます。さらに、両面使えるタイプなので、刃先がすり減ってきたら裏返して使うことができます。刃の付け替えも工具なしで簡単にできるし、金属と違って手を傷つけにくいです。また刃の範囲はタイヤの外形に合わせ、壁際まで刈れるのもポイントです。

「ハンターxハンガー」を製作するきっかけとなったシカが、淵岡さんの作業風景を見守る。
今回は最初から樹脂刃が本命やったね。人だけでなく壁際を刈る際に壁を傷つけるリスクもあるので、総合的にみて「奥さんが気軽に草刈りに使う」という視点なら、樹脂刃が最適です。
ただ実は今、インサート成形で薄い金属を樹脂に挟んで一体化させた刃も試作中です。金属がむき出しでない分安全性を担保しつつ、樹脂だけのものよりは切れ味を良くして、芝刈り用途で刃を付け替えられるようにできたら良さそうかなと思って。こうした試作がすぐできるのも「INARI P35」の良さやね。

オプションとして開発中の金属入りの刃は、SUS304のステンレスをファイバーレーザーでカットして、「INARI P35」でインサート成形している。
「完成した喜び」が、やり続ける原動力になっていく。
もちろんです。京都の工房も整理して伊那に集約したいと思っていて、今作業している工房のほか年始にもうひとつ工房を建てました。それでも京都の工房よりは狭くはなりそうですが、その分工夫してやっていこかなぁって思ってます。この場所だからこそ生まれるゆったりとした時間と綺麗な景色、空気感が Fielder's のものづくりにとって欠かせないんです。

新倉庫の片隅で次の出番を待つ、魔改造された「MAGEMAGE」の前モデル「Bender Black 30」。動力源を手動式から油圧式にしたことで、さらに厚い板や幅の広い板を曲げることが可能になっている。
まぁ人それぞれやから難しいけど。たぶんね、なんでそれが好きか、なんのためにそれをしたいのかをできるだけ明確にして、それを自分自身で客観視できなあかん気がしますね。5年後10年後に自分がどうなっていたいのかを具体的にイメージして、それを実現するためやり続けられるかどうかやと思います。
「ものづくり」においてやりたいことを実現していくための原動力言うたら、絶対「完成した喜び」やね。出来上がったときの「あ、やり遂げた」っていう感触の喜びを一回知ってしまうと、もうやめられんよね。だからまずは何でも良いから「やり遂げ」て、それが自分に合ってたかどうかをフィードバックして。そうしないと何しても中途半端で、喜びもないままでやめていくことになるのかなと思います。
やり続けて、やり遂げて、喜びを知る。そうしたら「好き」になる。こんな感じで「好き」が仕事になっていくんでしょうね。僕自身も20年前には今の自分が想像できていたわけではなくて、とりあえず目の前のことをがむしゃらにやり続けて、やり遂げてきた。気がついたら今になっていた。それだけなんで。
「ゆきちゃん」の次も、もうちょっと草刈りシリーズを頑張りたいかなと思ってます。次のテーマは、田んぼの草刈り機のロボット化。
田んぼの草刈りってすんごい大変なんですよ。田んぼの周りのウネはほとんどが急な斜面で、完全自走の芝刈りロボットなどでは対応できません。あと田んぼのあぜ道や斜面用の自走式草刈機とかもあるんやけど、こっちは操縦が難しいし重いしなかなか思い通りに進んでくれません。
だから田んぼの草刈りを、もう一歩どうにかしてあげたい気がしてます。実はアイデアの特許はもう出願してるんです。実装するのがまた結構大変なんやけど。それはそれでぼちぼちやっていきたいなと思ってます。
関連記事
手づくりオーダー眼鏡フレーム工房「澤口眼鏡舎」を立ち上げ、お客様に寄り添いながら1本1本をつくり込む眼鏡作家、澤口亮さんにお話を聞きました。
【クリエーターたち】国立研究開発法人産業技術総合研究所 阿多誠介 インタビュー
カタチや機能で表現される全てのモノは「何か」でつくられている。今回は、その「何か=素材や材料」を複合材料の視点で探求し続ける研究者、阿多誠介さんにお話を聞きました。
オリジナルブランド「colm」を立ち上げ、CNCによる切削加工と伝統技法「革絞り」を組み合わせたレザーアイテムを展開するプロダクトデザイナー、成田吉宣さんにお話を聞きました。